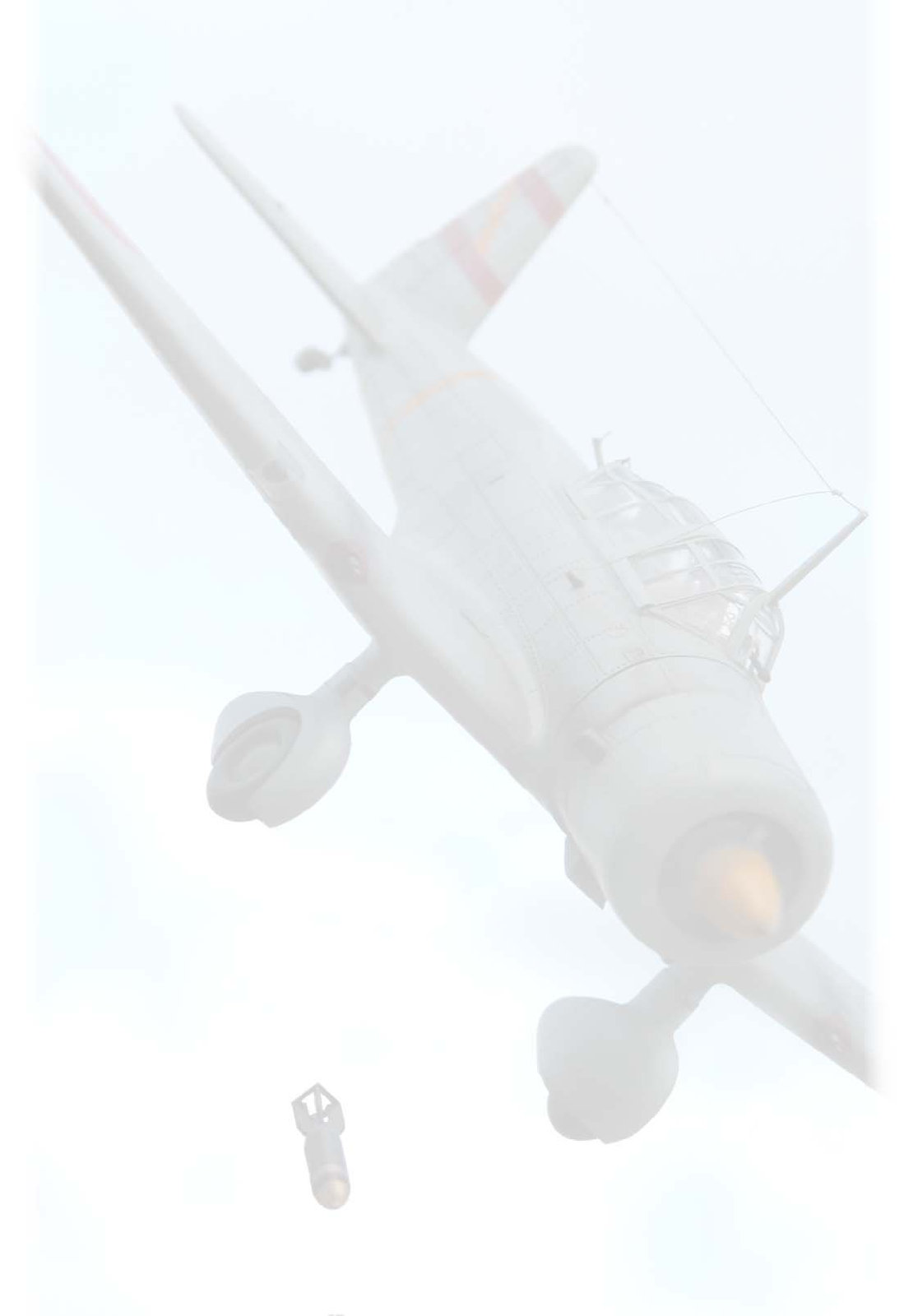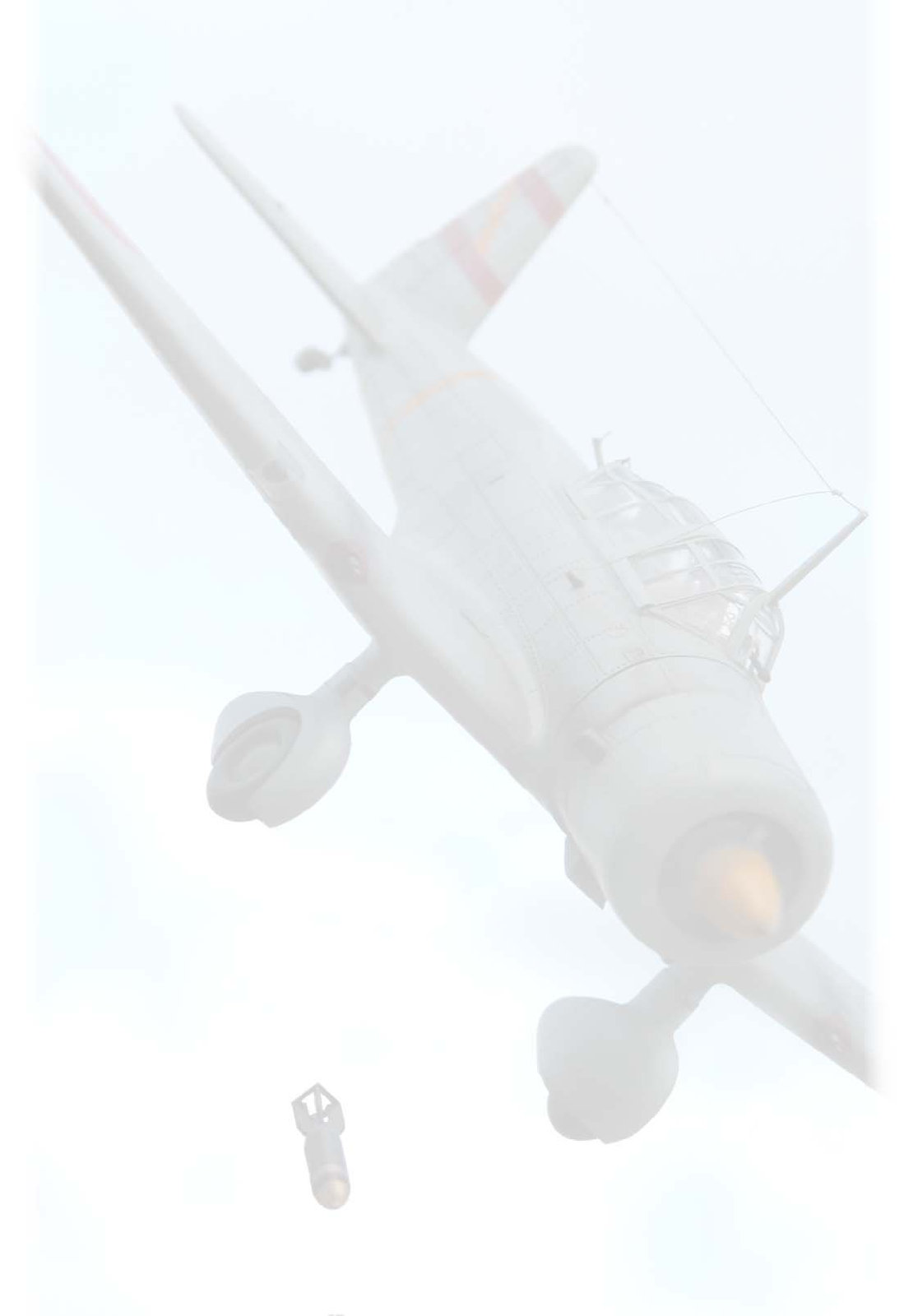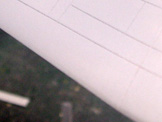珍品!?チェコ製帝国陸軍試作戦闘機『キ-64』制作記 その3
2009 4/4(土)
キャノピーを被せるとこんな感じ。なんとなく全体が見えてきました。胴体の細さ、頭の小ささなど、国産飛行機とは思えない形をしています。完成が楽しみになってきました。
パイロットを載せるつもりなのですが、当然キットにはついていないのでハセガワの1/72パイロットフィギアセットから持ってきました。
このハセガワのパイロットフィギア、陸軍のパイロットは搭乗しようと片足を上げているポーズなのですが、単独で見ると、しつこくつきまとうポン引きに蹴りを入れている短気なオヤジにしか見えません。なんでこんな使いづらいポーズを設定したのか非常に不思議なのですが、これでは改造しようにも無理があり過ぎ(笑)
しかたがないので海軍パイロットを陸軍風にして使います。色の着いていないのが元。こやつもポーズを着けているのですが、四肢は切断してしまいます。飛行帽の耳当てがはねているのですが、これもちょん切ってパテでちゃんと耳に当てます。酸素マスクと襟もパテで追加し、最後に四肢をパテで作り直し色をつけました。
コクピットが狭い上に、足元にコントラペラのシャフトとギアがあるので、すり合わせながらポーズをつけるのに非常に苦労しました。



さてアウトラインがハッキリしてきたので、細かいディテールアップに入ります。まず機首まわり。今回このキ-64は実験機としてではなく、部隊配備された状態で仕上げるつもりなので、当然武装が必要になります。両翼に20mm、機首に12.7mmもしくは20mmと三式戦飛燕なみの武装が想定されるのですが、機首の機銃用の溝を再現するのは至難の技です。外板とほぼ平行に穴を開けなくてはなりません。しかも2本。これはむずかしい・・・色々悩んだ末、奥の手を使います。
写真はファインモールドの三式戦のものです。聡明なる読者諸氏ご存知のようにキ-64はキ-61(飛燕)製作の延長線上にある機体で、機体デザインから各種レイアウトまで至るところにその類似性が見られます。この製作記冒頭で触れたように私は最初パッケージを見て飛燕と勘違いしたほどです。
つまりはこのファインモールドのキットから部品を持ってこようという訳です。とはいえ、飛燕だっていつか作るつもりなのでAパーツのみ限定での流用とします。
Aパーツはメーカーに部品請求します。送料込み700円です。
写真のように慎重にエッチングノコで当該部分を切り、ファインモールドのパーツを当てて見ると多少の段差はありましたが、修正可能範囲でした。
2009 4/5(日)
キットのコクピット部品……床。計器板。椅子。操縦桿。以上!!これではどうしようもありません。ファインモールド飛燕のAパーツを流用しつつ、それ以外は全部作り直します。無論キ-64のコクピットの資料などないのですが、松本市図書館から「丸メカ」飛燕の縮刷版、学研「三式戦飛燕・五式戦」を借りて来ました。ああ素晴らしきかな空港図書館。こいつを参考にデッチ上げます。
2009 4/12(日)
プラ板、伸ばしランナーで作ってみました。機体が完成すれば椅子の上のあたりしか見えなくなってしまうのですが、まあこんなところまで作るのは趣味ならではですかな。適当ではありますが。機体内部色は学研の「三式戦飛燕・五式戦」によると(五式戦は、という前提ですが)黄緑七号色ということになっているようです。そんな難しい色を持ち出して来たところで、再現するのは無理ではないかという危惧があったのですが、学研のくだんの本に掲載の色見本がMr.カラーのカーキグリーンに近いので、ためらうことなくこれを採用しました。
パイロットを載せるとこんな感じ。ギア部分に足が触れないように短足体型にして、股を広げさせ、さらに足を上げさせています。非常に苦痛を強いられる態勢ではあります。
こんな按配で胴体左側もちょこちょこでっち上げようと思ったのですが、パイロットを載せて左右合わせて見ると、もう左側には全然余裕がないので左側はオミットに決定。平行して進めているナナニー雷電のコクピットと比べるとこの液冷戦闘機は半分くらいしかないのではないでしょうか。


主翼。上下パーツを合わせてみたのですが、こちらを合わせるとあちらに隙間が、隙間を押さえるとこちらが開くいうドリフのコントのような状態になってしまうので、ありったけのセンタクバサミなどで押さえながら接着しました。こうして写真で見ると、70年代のあばんぎゃるどな前衛芸術作品のような趣があり、いとおかし。
さらに左右の翼の厚さが違うので、万力で適当な圧を加えて均等にします。厚さを測るには、現在当情況劇場が最も自慢できる工具『デジタルノギス1号』が大活躍。1号って2号はないけど。
このキ-64というヒコーキは液冷戦闘機の宿命的な欠点の一つ、ラジエターのでっぱりをなくすというのが主眼の一つなのでした。しかし、ラジエターをなくしてしまうわけにもいかず、ではどこ持っていったかというとなんと翼内。蒸気冷却装置という裏技のようなものを使い、翼面を外気に晒すことによって冷やしてしまうという特殊な方法をとっています。さすが日本人。ダウンサイジングはお手の物。
・・・いやいきなり何を受け売りとしか思われない知識をひけらかすのかというと、このキット、他のナナニーのどの日本機のキットよりも翼が厚い。前述のように翼内に特殊な工作を施しているとはいっても、厚すぎるのではないか。特に後縁なんかボテボテでちょっと見、前か後ろか分かりません。これじゃ素人目でも力学的に宙に浮かないでしょう。
以上のようなごたくをトウトウと述べた上での結論。翼が厚いのは翼面冷却装置が入っているので大目に見よう。しかし後縁はゆるせん。激しく削りたおす!!。こういうことでよろしいでしょうか。
400番のサンペで、削り粉まみれになりながらガシガシ削りました。いや削ったつもりなのですが、後縁こそ線状に収斂されたのですが、そこに至るまでのラインがどうしても痩せない。とにかく全体的に厚いのです。これを満足いくまで薄くするにはカンナが必要になりそうなので、このへんで諦めました。ちなみにこんな写真では厚みなど一切わかりませんな。許してちょんまげ。