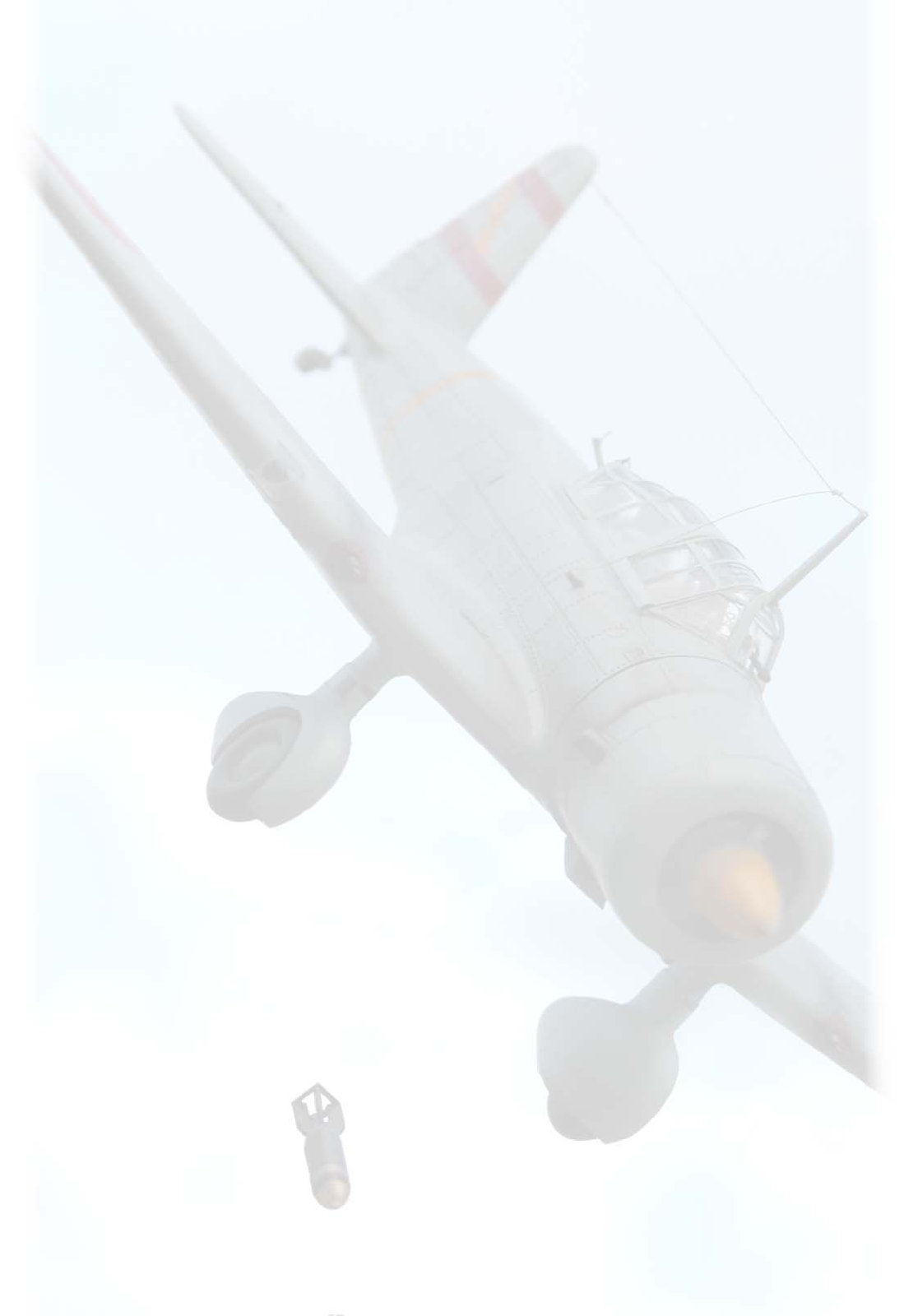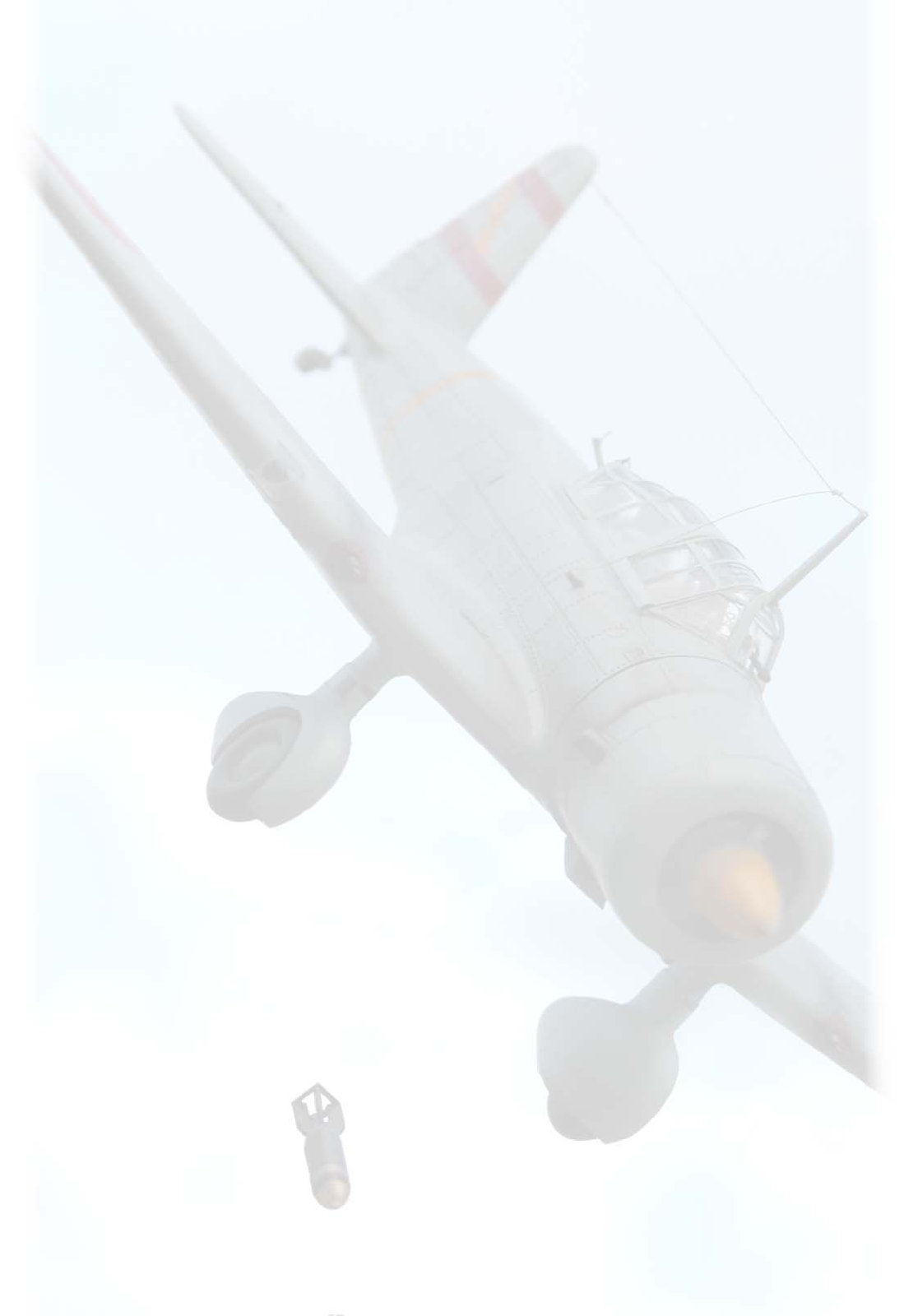ブラックバード?カラス? 九八式水偵を作る その4

2009 3/1(日)
で、黄色で塗った垂直尾翼に慎重に位置をきめつつ貼りこみます。この辺はデカールに頼ってしまった方が簡単に美しく仕上がるのでしょうが、あいにくこのキットのデカールにF-1の文字はありません。自作という手もあるのですが、アルプスプリンタのカセットインクでは、ブラックの地にイエローの文字では隠蔽度が低く裏映りしてしまいそうですし、シルバリングも発生しそうです。
パネルラインに沿ってフラットブラックを吹きました。これでパネルラインが強調されればもうけものなのですが、重ねる色がブラックに準じた色では、その効果は疑問です。ではなぜそんなことを?・・・いや実は昨年末、あまりの仕事の忙しさに耐えかね、『自分へのご褒美じゃ〜』とばかりにハンドピースを購入してしまい、その性能を見てみたかったからだったりします。買ったのはタミヤのトリガータイプ0.3mm。・・・と0.5mm。貴様2本も買ったのか。いやいや嫁さんがよくも許してくれたものよ。
さてその使用感なのですが、いややっぱりいいです。素晴らしいレスポンス。今まで使ってきたアズテックを悪く言うつもりはありませんが、このタミヤのトリガータイプには、『詰まる』だとか『暴発』というのはまずありません。実に素直に私のいうことを聞いてくれます。トリガータイプなので持ちやすいし、トリガーも引きやすい。素晴らし過ぎて、わたしには過ぎた道具という気もしますが・・・
全体の色ですが、軽巡搭載機仕様はブラックが指定色なのですが、そのままスミ一色で塗ったのではつまらないので、イマジネーションの働くままに色を変えてしまいます。実機は工場出荷時にはブラックで塗られているのでしょうが、紫外線に曝され、潮風にあたり続けると当然褪色が激しくなります。で、どんな色に転ぶか。私は赤系に転ぶ、いやつまり赤茶けるのではないかと思ったわけです。黒いTシャツなんか、洗濯するたびに赤茶けていくじゃないですか。これは私が安物のTシャツばかり着用しているという事実を証明するとともに、黒色は褪色すると赤っぽくなっていくということも明らかにしています。なので、ツヤ消しブラックにレッドブラウンとニュートラルグレーを混ぜたものを使ってみました。
さらにそれにレッドブラウンを追加投入したもので塗りにメリハリをつけて、一応塗り終わりました。ちなみに写真横の黒丸はRGB画面で見たいわゆるK(ブラック100%)です。塗り色が赤っぽいのが判りますでしょうか。
本来なら最後の最後までマーキングのマスキングは剥がさない方がよいのですが、せっかちな私はどんどん剥がしてしまいます。・・・どのマーキングもまあまあいい感じです。






2009 3/2(月)
上翼を立ち上げて張り線という制作の山場、佳境に入ります。まず、支柱を塗っておきます。写真の様に同じような部品ばかりなので、紙に両面テープを貼って部品を固定しては、部品番号を書いていきます。そうしないと、どの部品ががどの部分にあてはまるのか訳がわからなくなってしまいます。
真鍮線の入っている桁(支柱)を下翼の電極穴につっこむと、一応上翼は固定されるので、その状態で他の支柱を瞬間接着剤で固定していくのですが・・・この作業が思ったより難しい。下翼のくぼみに部品を刺しこもうとすると上翼が視界をさえぎるし、上翼に固定しようとするには、下から覗き込まなければなりません。むろん夜の作業なので、光の当たらない下面は真っ暗です。せっかく思い入れたっぷりに塗った赤茶けたブラックの翼のそこここを瞬間接着剤で汚しつつ、信州の夜はふけていきます。
が、2時間ほどの悪戦苦闘の末、全ての支柱の接着に成功。全て点着けなので強度的に心配だったのですが、結構頑丈に上翼は固定されていました。
作業後半になって、部品の方に接着剤を着けると、孔を探っているうちにそこらを接着剤で汚してしまうので、孔の方に接着剤をたらしておけばいいと気が付いたのですが、そんなことに気が付いた頃にはもう作業は終りに近づいてました。よ〜し今度作る時は・・・しばらくこんなことしたくないか。
しかたがないので汚れの激しいところはサンディング、微妙に部品が浮いているところなどはパテや『瞬間接着剤大量流しこみ硬化剤で速攻硬化』の荒技などを使い修正。結局部分的に塗りなおさねばならないことに。マスキングを剥がさねばよかった・・・
2009 3/7(土)
5日間の作業のはてに全ての張り線が終りました。逐一写真を撮っていけば良かったのですが、何しろ張り線作業をするだけでも手が4本程あればいいと思うほどなので、カメラを持ったりシャッターを押したりなんてとても無理。それぞれのヒートンに糸を通していけばいいだけの作業なのですが、翼に挟まれた狭い空間をあちこち糸を引き回し0.3mmの穴に糸を通すのは結構大変でした。それでも、ヒートンのおかげで前の九四式水偵の時のような苦労は感じませんでした。
2009 3/8(日)
ペラの塗装が最後に残っていました。ペラの材質等全く考えていなかったのですが、よくメールでサゼッションをいただく『ゼロ戦』トモ氏に木製ペラであることを教えられ、『ならば木目を描かねば』ということになりました。しかしうまい方法が見つからぬまま指定色のウッドブラウンを塗り、「さてどうしたものか・・・」。とりあえずコンパスの針で塗装を剥がす感じにカリカリとやって見ました。こんなんでどうでしょうか・・・と聞いて見てもトモ氏は遠くカナダの地に(ホームステイだそうです)
パテで修正したり瞬着硬化剤でしみができたりした部分を再び塗りなおします。最後までマスキングを剥がさなければ写真のような二度手間をせずにすんだものを。
半光沢の水性トップコートを吹き、いよいよクリアパーツ部分のマスキングを剥がします。結構大変だったのが、ぎっしりと支柱に囲まれたキャノピー後部。ピンセットがやっと入るような場所なので、多少時間がかかったのですがなんとか終了。