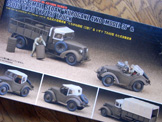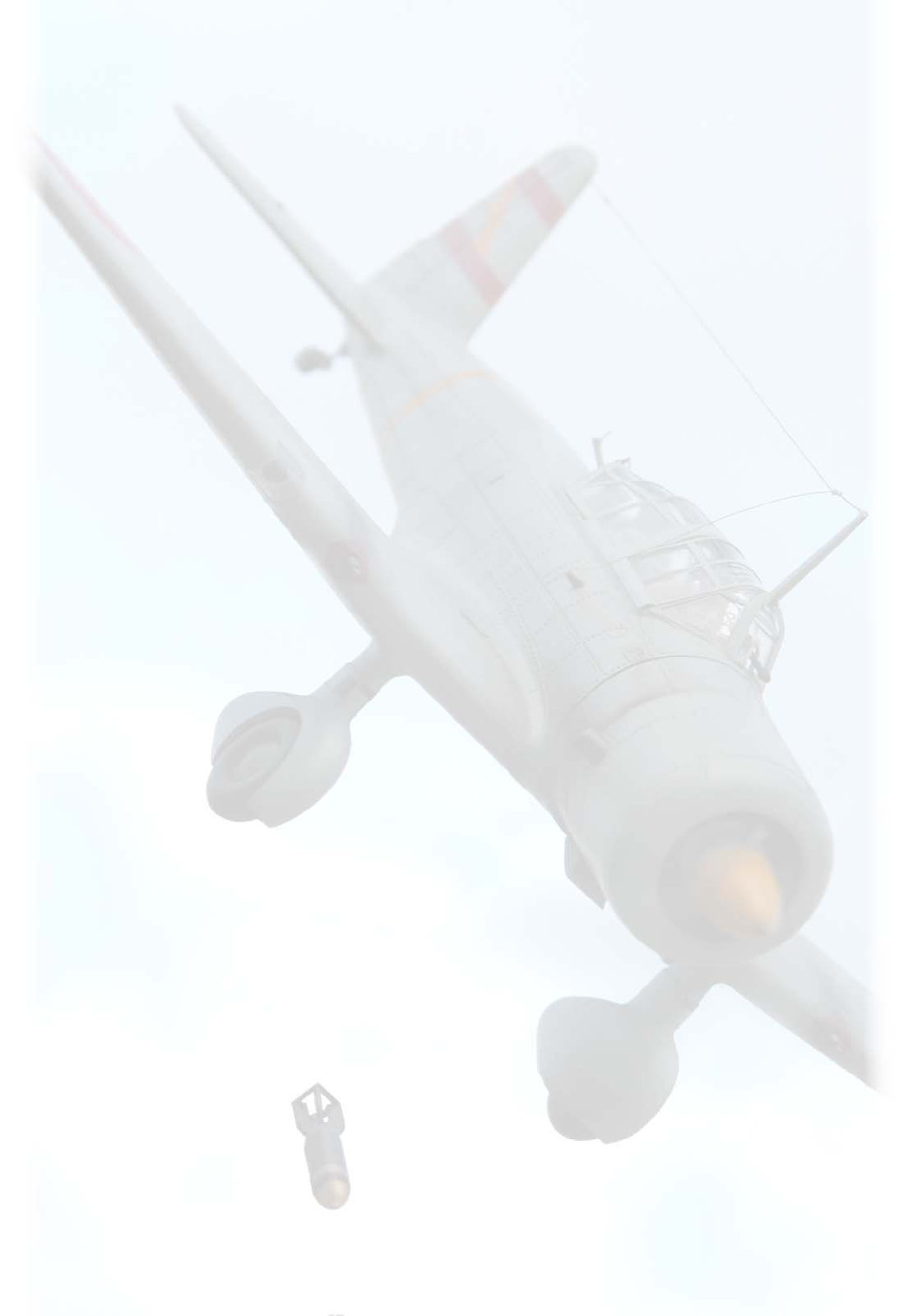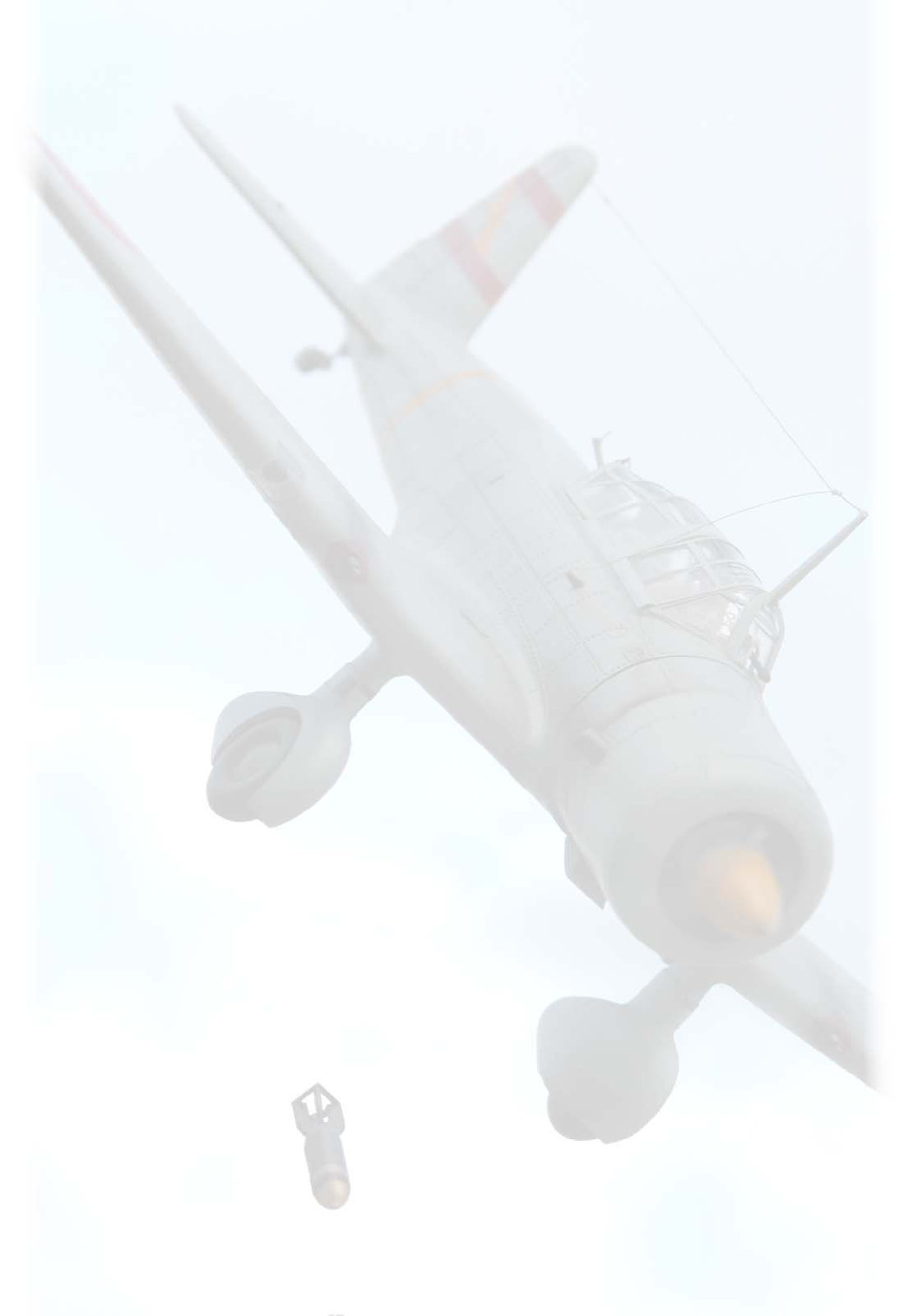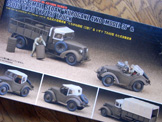『子供と作ろうF/A-18スーパーホーネットE』始末。その3
2010 8/15(日)
とりあえず、後輪2脚も仮組みしてみました。ここまではOK。
さて大抵の大戦機同様、スパホも脚は3つです。しかし、その構造は大戦機とは異なり、脚から脚庫のふた(ふたって・・・)からやたらフクザツな形状をしています。特に脚庫のふた部分は3分割の上にぎざぎざなデザインでおまけに微妙なRのついた部品まであります。おゆまるで部品の複製をしてみたのですが、こういう板状のものにはかたどりは不向きのようでうまいこといきません。やはり板状のものはプラ板から切り出した方がよいようです。
しかして、平らな部品はまあなんとかなるとして、前述の微妙なRのついた部品。問題はこれだ。プラ板では熱を加えないと、この微妙なR状態を保たせるのは難しそうです。そこで、最近お得意のアルミ板を使ってみました。なにせこの暑さでアルミ板の在庫は山のようにあります。いやあれだつまり最近ビールばかり飲んでいるのよ。この缶ビールから切り出したアルミ板はほどよい厚さで、簡単にハサミで切れるし、プラ板と違って曲げれば曲がったままでいるという素晴らしい特性をもった、貧乏アル中モデラー御用達の素材です。
2010 8/22(日)
スキャナで脚庫をスキャンして、脚庫の形状をトレスしプリントアウトし、それを元に平らな部分はプラ板を、Rのついた部分はアルミ板を切りだし、ちまちまとカタチを整えなんとか脚庫のふたが完成しました。
こうして見ると、怖気を震うほどガタガタなのですが、例によってここは映らないように写真を撮るので無問題。・・・って、それならそれで最初からオミットしちまえばいいようなものなのですが、それはそれでやはり『負けた』気がするのでいやいやながらやってしまうという・・・
前脚の方はおゆまる複製品でよさそうです。(これもガタガタですが・・・)脚まわりだけで2週間かかってしまうという、何とも歯がゆい進行具合ではありますが、サフをかけてペーパーでならしてこれでよしとします。
さて、細かいところをちょこちょこ修正したら、いよいよ色塗り、デカールと完成作業に入ります。

2010 8/29(日)
キット付属の組説は、上面をつや消し白5対ナントカグレー1の混色したものでとか面倒な指定になっています。5対1などといっても、量の測りようがないし、どのくらいの量を作ればいいのかわからないので、ビン生ダイレクトでOKな色を探します。そんなのネットで探せば簡単だと思っていたのですが、『F/A18、私はこの色で塗った』とか『現用アメリカ海軍機はミスターカラーではこの色とこの色の組み合わせです』などという都合のいい記述がなかなか見当たりません。そりゃそうだ。キットのインスト通り塗れば、わざわざこの色塗りましたなどと記述はしないだろうし、そもそも現用機を作っている人には常識以前のことで、記述する必要のない事なのでしょう。
それでもしつこく探しまくって、ようやく写真の色であることをつきとめました。307(濃い方)が上面色、308が下面色です。101スモークグレーは汚しにつかいます。
さっそくタミヤのトリガータイプ0.5mmノズルを使い上面色から塗ってみました
。ところが、気温が高くて乾燥しているせいか、ちょっと遠目から吹くと表面が粉吹き状になってしまいます。考えて見ればこの高温乾燥状態で塗装をするという経験はほとんどなく、これには驚きました。そういや嫁が「毎日暑いのは困るが、洗濯物がすぐに乾くのだけは助かる」とのたまっておりましたな。
そこまで終らせて、ちょっと子供を連れて買い物に出ました。実は近所にある飛行機模型を主にした模型屋がこの31日で閉店するとのことで、全品半額セールを行っているというので出かけてみたのですが、目当てにしていたものはとうの昔になくなっており、かといって客が私と息子の二人だけでは、お茶を濁して店を立ち去るわけにもいかない雰囲気で、血迷った挙句、まったく作る予定のないくろがね四起と九七式自動貨車のセットなどを購入してしまいました。まあいいか半額だし。いずれ作ることもあるでしょう。しかし、また1軒模型屋が松本近辺から姿を消してしまいます。残念です。
2010 9/4(土)
閑話休題。308番で下面も塗り、汚しをします。101スモークグレーをシンナーでシャバシャバに薄め、パネルラインに沿って吹きます。乾いたところで308をシャバシャバにしたものでスモークグレーが微妙に残るように調子をつけます。上面も同じように。実はこれ307と308の記述があったサイトの方がやっておられた方法で、完成品が素敵にスバラシかったので真似させていただきました。