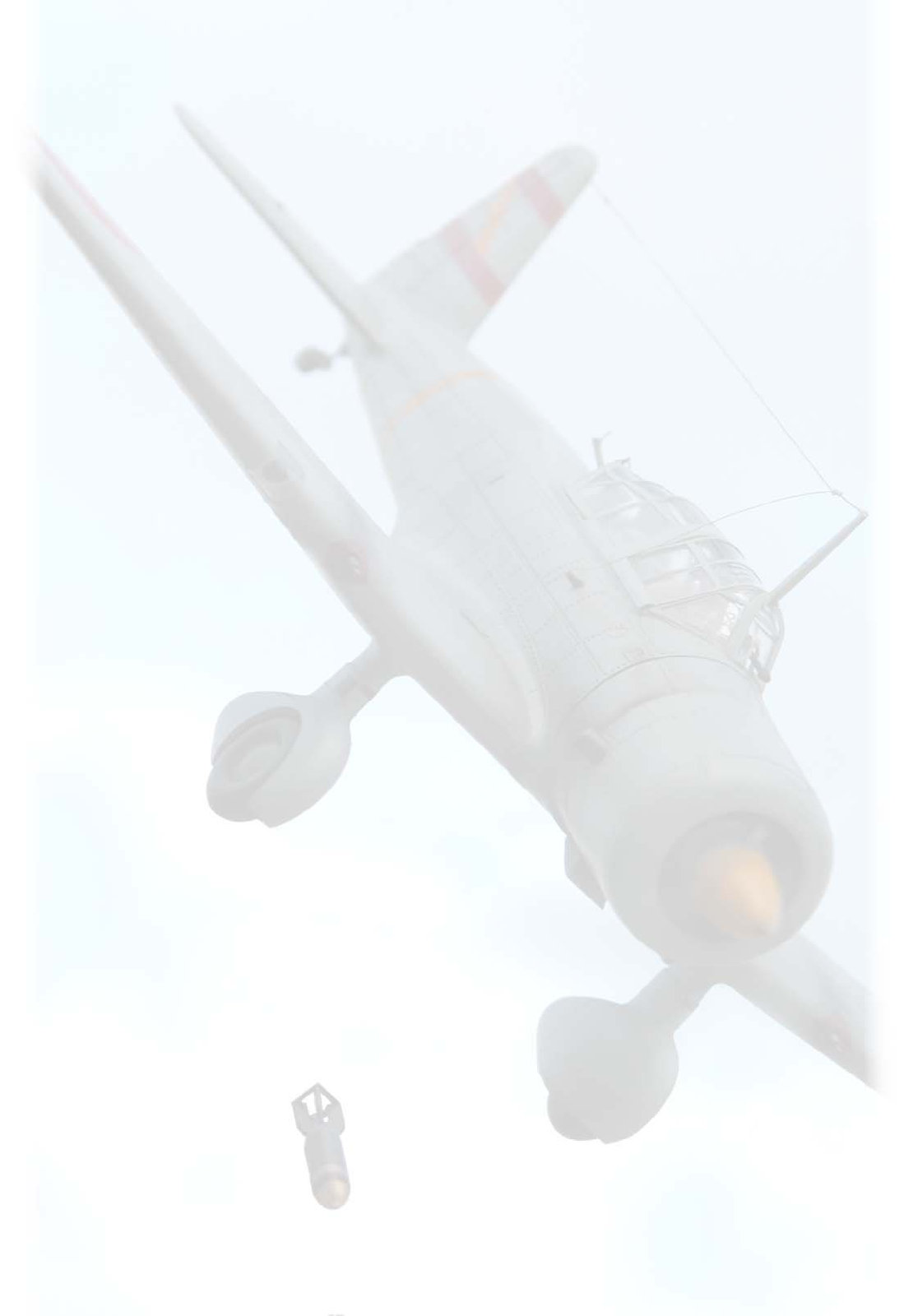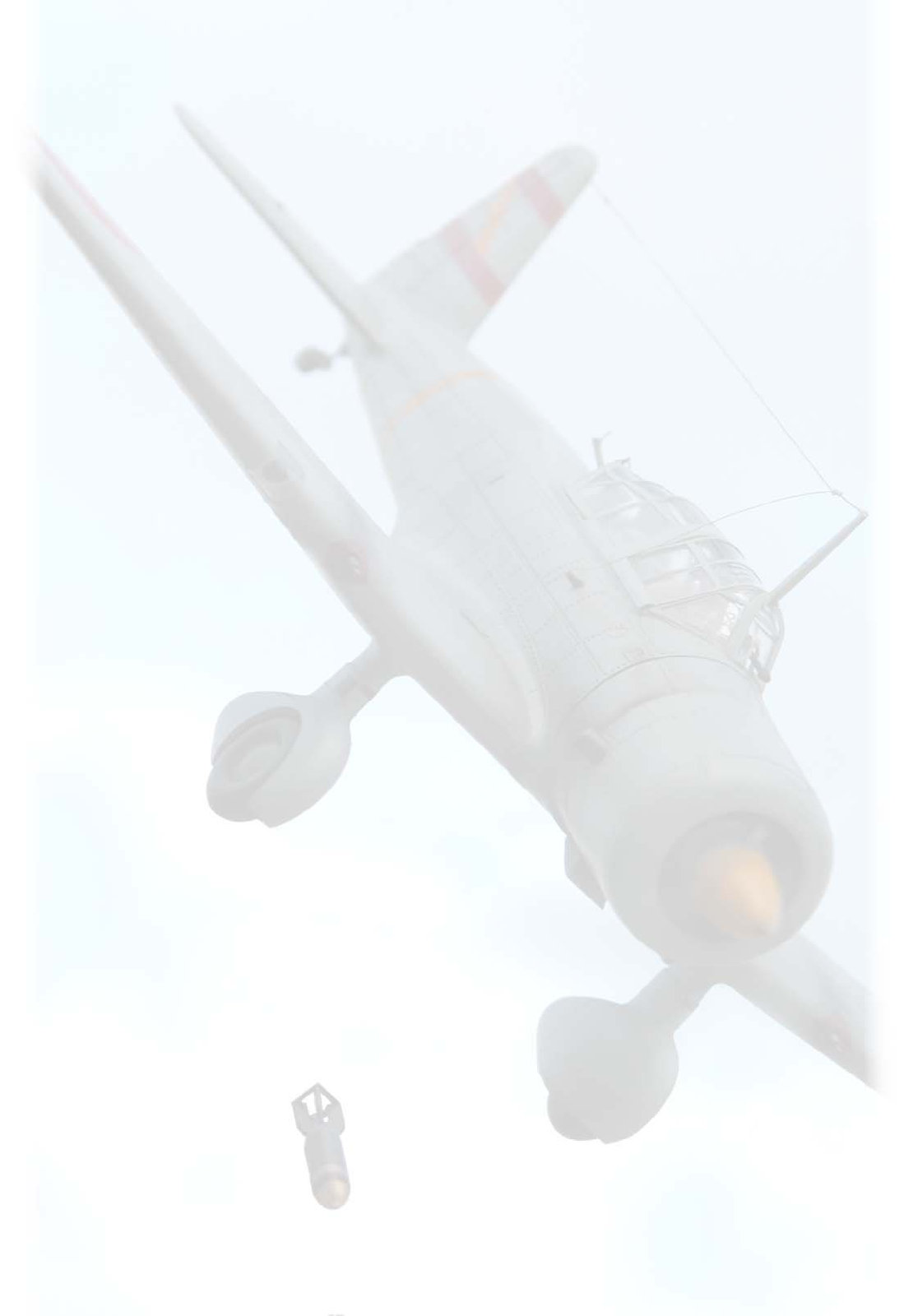たまには水物・・・軽巡川内を作る その5
2010 4/18(日)
ダビット。キットのものは1種類。丸スペシャルに掲載された写真にきれいにダビットが映っているものがあるのですが、よく見るとダビットは2種類あります。一つは素材が丸棒で小ぶりで甲板に固定してあるもの。もう一つは素材がH型の鋼材で大きく舷側に固定されています。しかるにこのキット付属のものはサイズといいカタチといい微妙に違います。という訳でこれも作ります。
適当な太さの柔らかい針金(素材が何かは忘れてしまいました)を写真のように曲げて作りました。これは小さい方。こいつは甲板に穴を開けて埋めこみます。大きい方は同じように曲げたものを金床の上でトンカチで叩き平たくつぶして板状にして長さを揃えます。舷側に固定する部分は伸ばしランナーにピンバイスで穴を開けチューブ状にしたものを短く切って作りました。
写真のようにキットのものよりかなり大きくなっています。
ネットで色々調べてみると、川内にはやはり2種類のダビットが搭載されているらしく、小さいものは短艇用、大きいものは内火艇のような大型艇に使われていたようです。
しかし丸スペシャルを購入してしまったおかげで色々なことが解ってしまい、解ってしまった限り看過できないという性格が災いして手間がかかるかかる。たかだか軽巡一隻に3ヶ月かかってしまいました。絞め切りがあるわけでもなし、とことんやるか。
2010 5/4(祝)
内火艇と短艇。キットのままでは味気ないのでちょびっと味付け。操舵室を透明アクリ角材に置き換えてカタチばかりとはいえ窓ガラスぽっくしてみました。アクリル角材を削ってカタチを出すのには、小さいものだけに苦労しました。もっときれいに磨いて透明度を増せば尚よいのですが、とにかく保持してヤスリをかけるという作業がままならずこの程度で諦めました。
エッチングラッタルの小さいのを使って艇首甲板に手摺りをつけ、艇最後部には0.3mm程度の銅線をわっかにして作った浮輪をつけまいした。さらに内火艇、短艇とも舷側に伸ばしランナーでフチを付けて、ネットで集めてきた資料を参考に色付けをして完成。
ちょびっと味付けとか言いながら、この作業に1週間かかり大型連休に突入してしまいました。
で、いよいよ先のダビットを付けた甲板に内火艇、カッターをアクリル接着剤で固定しました。だいぶ雰囲気が出てきました。あと一歩で完成・・・なのですが、連休中は子供の相手をせねばならず、足踏み状態が続きそうす。って子供のせいにしてますが。
2010 5/9(日)
いよいよ最後の難関、張り線です。
まずは、前檣と後檣回りを集中的に。丸スペの写真など見ると、艦橋といわず煙突といわずありとあらゆる所に太い索やら細い索やらが、艦を縛り付けるがごとく張り巡らされております。当然これを全て再現することは不可能なので、雰囲気出しのために張るのですが・・・
2010 5/15(土)
0.4号のテグスを使い、乏しい資料と首っ引きで更に想像を交え、有体に言うと適当に張り線をしていきます。艦首から前檣と後檣のマストヤードを経由するものは長いので、本当ならば電線の自重でたわむはずなのですが(特に前檣と後檣の間など)程よくたわませるというのがテグスでは難しくやむなくピンと張ってしまいました。
ネットで得た知識なのですが、テグスをマストヤードなどに点着けする時は、瞬間接着材のトロトロのとゼリーのを適宜ミックスして使うと適度に初期接着力があり、しかもゆるいのでうまく全体に回りやすくこれはおぬぬめです。
さて、最後にアンカーと菊の紋章を着け、茶色パステルで適当に汚して一応これで完成とします。
制作開始から4ヶ月が過ぎ、後半はもうすっかり飽きてしまったのですが、無駄に制作期間が長引くと制作意欲が薄れ、ますます冗長になってしまうという良くないスパイラルにはまってしまいました。この次は、この次こそはサクサクッと気軽に組上げたいな。などと祈念しつつ。制作終了。
2010 5/16(日)
とりあえず晴天なので、自然光で撮ってみました。まあこの程度が私のモデリングの限界でしょう。逆光で撮ればエッチングの射出機のディテールとあいまっていい按配です。
さて、昨年完成した九八夜偵と組み合わせて『情況』をでっち上げます。しばしお待ちを。