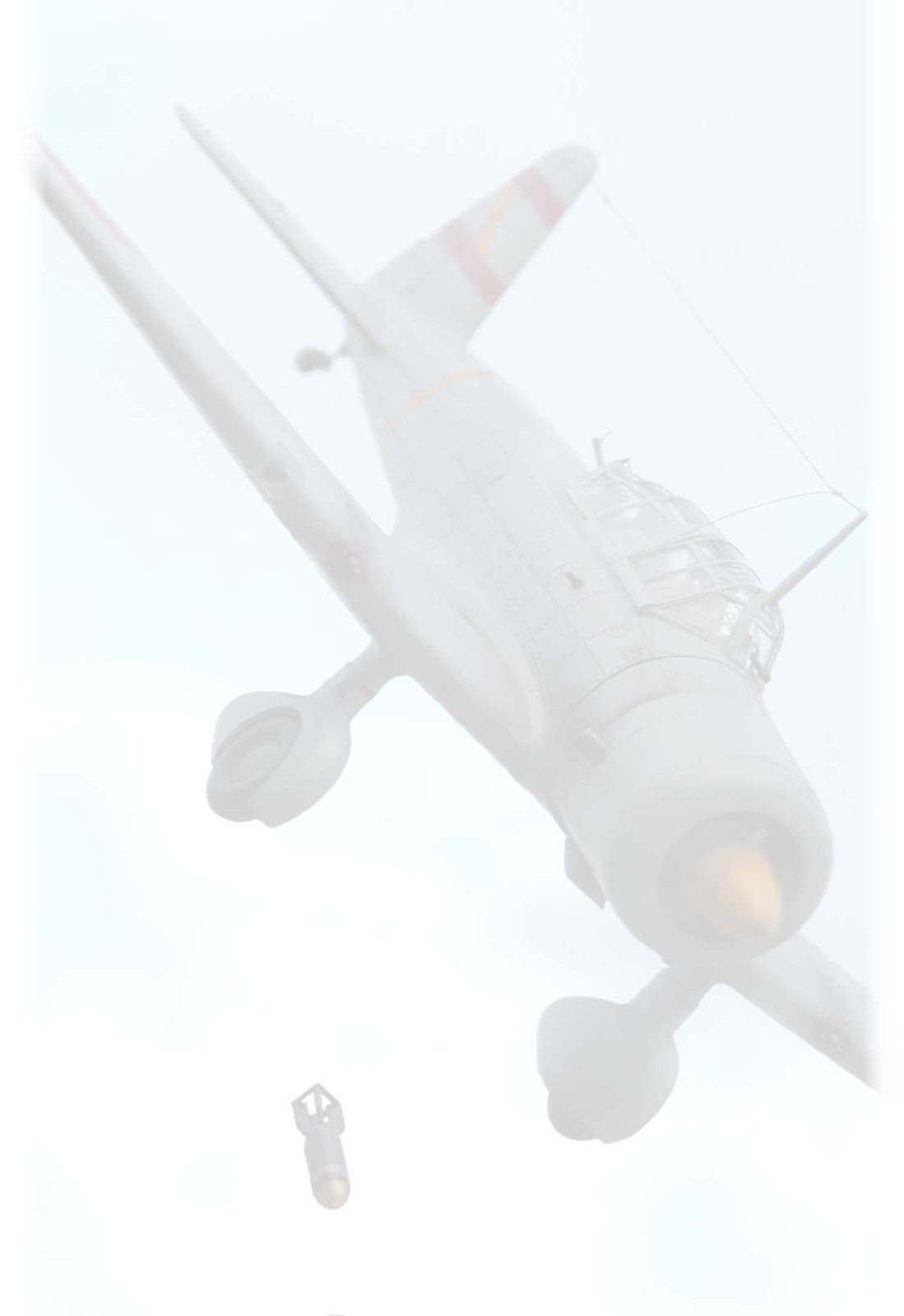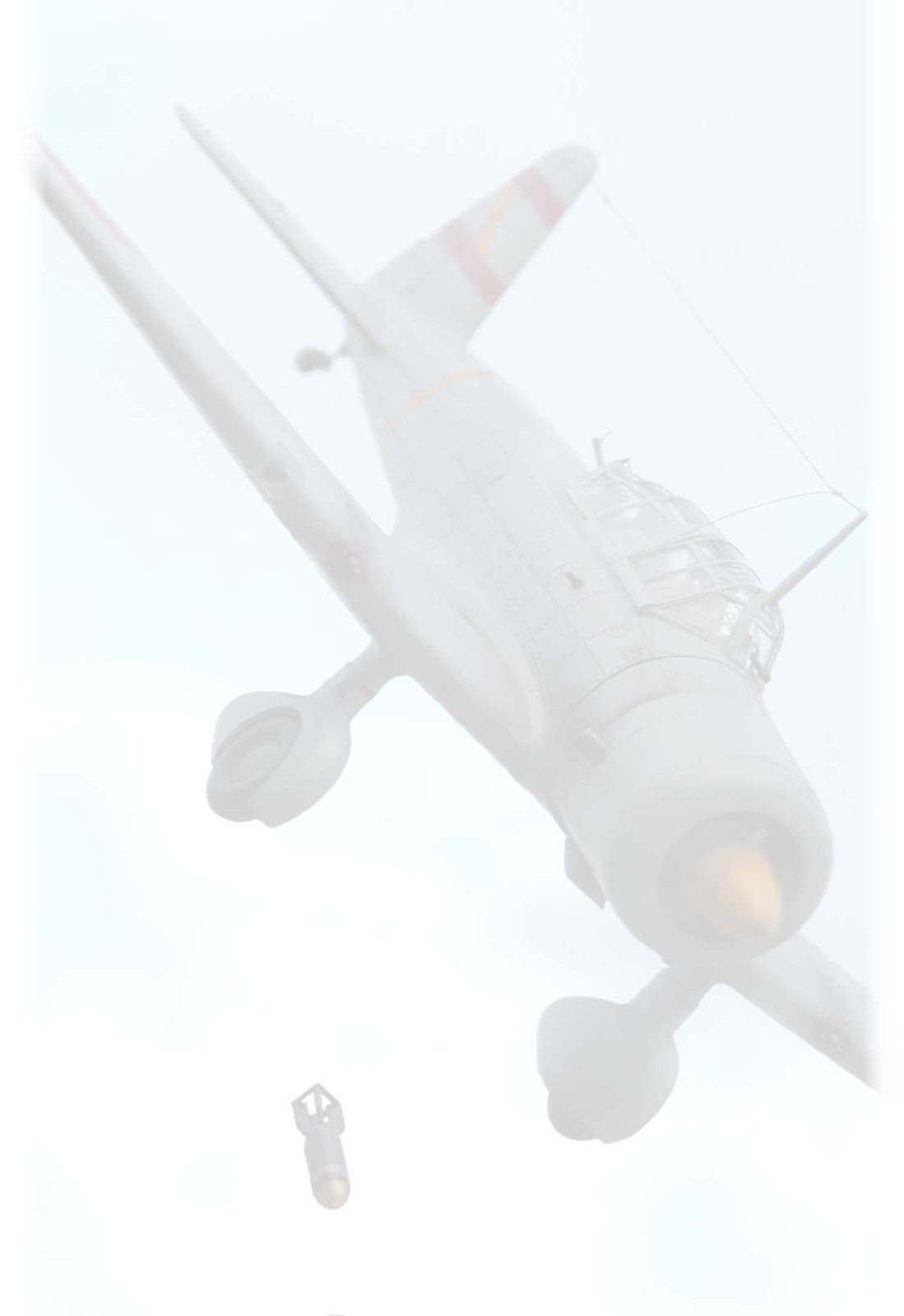再開!ハセガワ72『雷電21型』02
2009 10/17(土)
サフ掛けも終り、全体のフォルムが決まったので、塗りに入りました。
まずは味方識別帯を黄橙色で塗り、マスキングします。
2009 10/27(火)
で、ひっくり返して下面色を塗ろうと思ったのですが、尾輪部分の処理をまったく考えていませんでした。塗ったあとで色々いじるのもいやなので、塗り作業を中断して、尾輪引っ込み状態のものをランナーでちょこちょこと作りました。まあ、こんなもんでしょうか。
下面色は定番クレオスの三菱系下面色。今まで作ってきた雷電は全てこれで通してきたので、踏襲。
2009 11/4(水)
下面色をとりあえず塗ってしばらく放置しておいたのですが、しっかり乾いたようなので、下面を一面マスキング。いやいや放置していたのは他でもない、主翼の裏、前縁部分にまで上面暗緑色が回りこんでいるので、その部分を残してマスキングするにはパソコンで作図してプリンターで紙出ししないといけないという、めんどうな作業があるからなのでした。なにしろここ3ヶ月ほど、自宅のパソコンおよびプリンタに電源を入れたことがないので、ちゃんと使えるのかしら。というテイタラクです。
2009 11/10(火)
さて、とパソコンのパワーキーを押すのですが、これが『ウン』とも『スン』ともいわない。やはり壊れてしまったかと焦りかけたのですが、これは長年の経験で、電源コードかキーボードのケーブルが抜けている場合がほとんどで、案の定キーボードのケーブルが抜けかけていました。古いMacはキーボードにパワーキーが付いています。でプリンターのスイッチを押したのですが、こいつも沈黙したままです。『またまたアルプスちゃんてば』などとアルプスプリンターの機嫌を伺いつつスイッチを押しつづけるのですが、これはもういけません。おなくなりになっています。大抵の機械は叩けば直るのですが(そんなことをしてはいけませぬ)叩いてもなおりません。・・・・・・・・・・「さて、バラすか。」
苦闘2時間。スイッチ部分を露出させるまでのフィールドストリッピングに成功しました。どうやらスイッチの接点部分が汚れいたようで、無事修理完了。もう十数年使ってますから・・・壊れもするわな。
などとほざいているうちに上面塗装が終了しました。
2009 11/15(日)
今まで作って来た色々なサイズの雷電は、全て日の丸はデカール処理をしてきました。何故と問われれば、それは面倒だから。なかんずく白縁と日の丸部分のバランスをとるのがとってもとってもめんどくさい・・・という実も蓋もない理由とともに、どうもサークルカッターで切り出したマスキングがぼそぼそで、ブラシを吹くとやはりぼそぼそな仕上がりになってしまうという実績があるためだったりするのですが、今回は敢えてチャレンジしました。つらつら考えるに、ぼそぼそな切り口になるのはカッターの刃を換えてないからではないかと思い、思い切って換えて切って見ると・・・これがスパッと一発で切りぬけるわけです。やはりカッターの刃はケチらず交換すべし・・・とまあ、つまらない結論に達しました。
写真のようにまあまあきれいに出来ました。白フチと日の丸のバランスも概ね良好です。・・・やれば出来るじゃないか、俺。
鼻ッ先のアンチグレアもつや消し黒で塗り、味方識別帯部分のマスキングを剥がすと・・・ようやく雷電らしくなってきました。



2009 11/21(土)
20mm機銃の長い方。0.7mm真鍮パイプを適宜切り、先端をライターで炙って・・・吸引すると疲れが取れて家事がはかどるの・・・って それはノリ●。ちなみに●の部分をピー音に置きかえるとそのヒトずばりになってしまいます。きさままた訳のわからんゴタクを並べて文字数を稼ごうとしおって。すみません。そんなわけで、・・・炙ってリーマーでぐりぐりして先端をロート状に広げます。
発動機部分。強冷却ファンはブレードを薄く削りカタチを整えました。センターにゴムを埋めこみモーターから来る動力軸を銜えます。さらに、ここにペラ、スピンナーを接着すればこれら部品が一体となって回転する・・・はずです。動力部分は作りがやわだと崩壊してしまうので・・・この場合具体的にいうと、屋外で撮影中にペラ部分がモーターの力でどこかにすっ飛んでしまう恐れがあるので、強冷ファンに真鍮線のダボを2本埋めこみペラ・スピンナー部分と接合します。
ところでこの写真をよ〜く見ると、若干動力軸がセンターからずれています。ウヒャ〜またやってしまった。1/100雷電もセンターが狂ったのですが・・・幸いこの状態でもモーターは回りますが。
この機体は、赤松中尉機として仕上げるのでデカールを自作しました。機番はヨD-1195、機番の下に赤松中尉という文字が入ります。この辺がよくわからないのですが、海陸軍とも各パイロット専用機というものはあったのでしょうか。母艦運用機は離着艦の時、機体のくせを知りつくしておかないと失敗する恐れがあるので、それぞれ専用だったと何かで読んだことがありますが、陸上基地ではではどうだったのでしょうか。今回の場合の赤松中尉と書いた機体は、タミヤのヨンパチにそのデカールがあり、デカールがあるというからには実際にそんな写真があったのでしょうが、赤松中尉ほどの古参パイロットには専用機が与えらるとか、そういうことなのでしょうか。