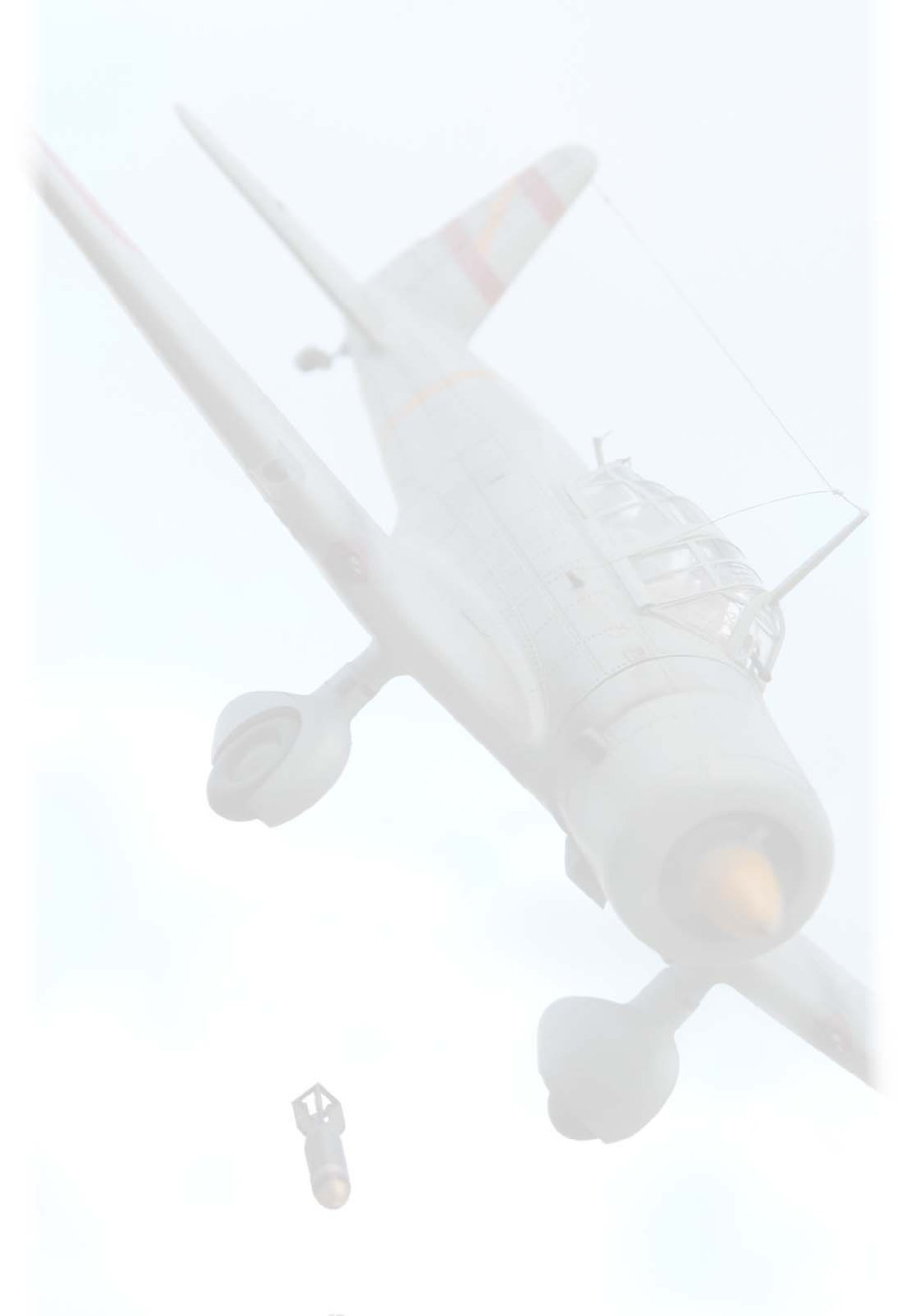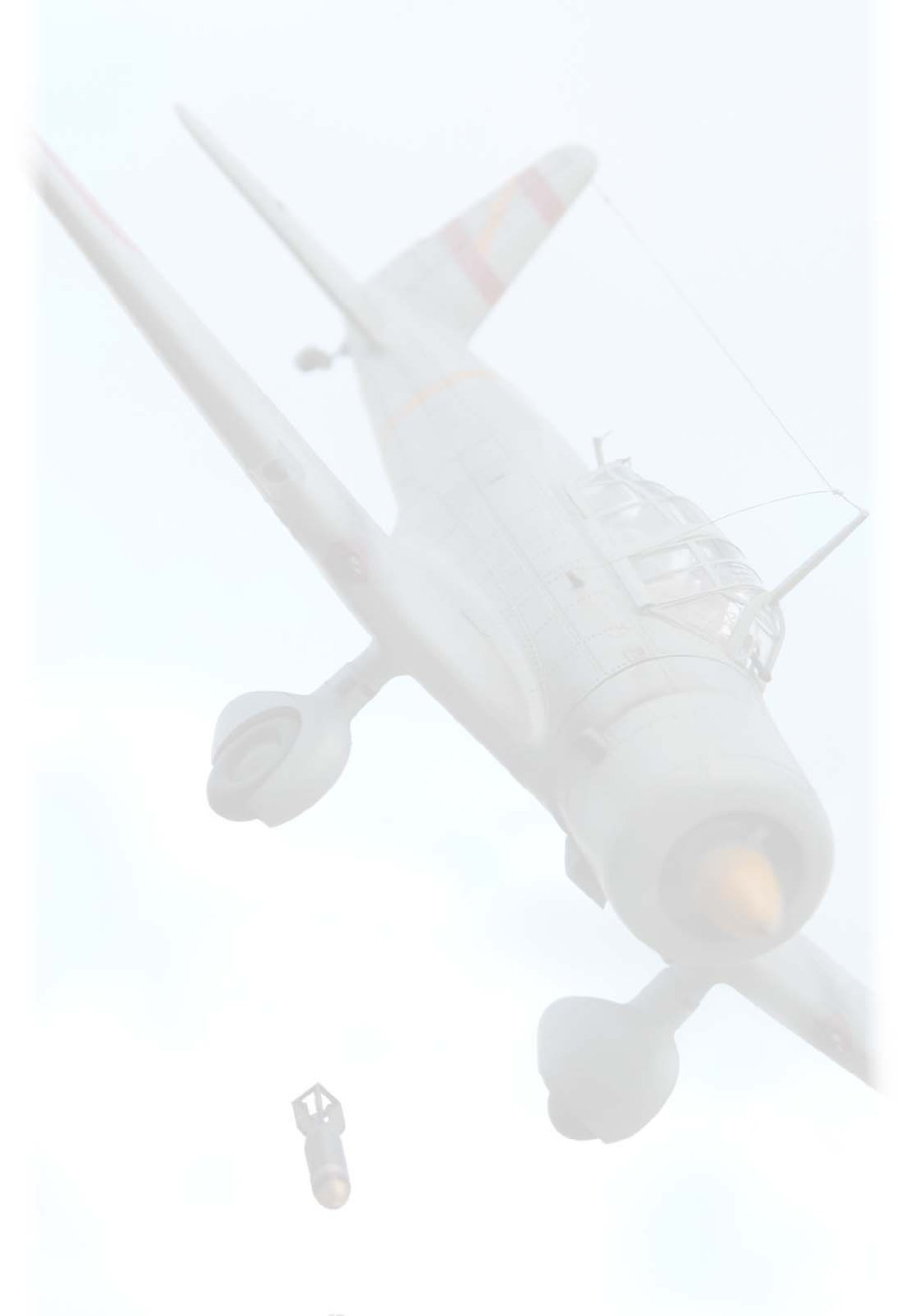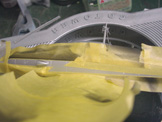���i�I�H�`�F�R���鍑���R����퓬�@�w�L-64�x����L�@����8
2009�@7/4�i�y�j
�@�悤�₭�L���m�s�[���ɃP���������̂Ŗ{�̂̍H��ɖ߂�܂��B
�@����A����ki-64�́w���̂P�@����@�Ƃ��āA��s�p���Ł��r���o������ԂŔ�s���r���o������ԂŃu�c�B��x�@�w���̂Q�@�������{�����퓬�@�Ƃ��āA��s�p���Ł��r���o������ԂŔ�s���r���o������ԂŃu�c�B��x�ƁA�ЂƂ̋@�̂�6�{�����������킨���Ǝv���Ă���̂ŁA�܂��͋r�����܂�����Ԃɂ��܂��B�L�b�g�I���W�i���̕��i�ōǂ����̂ł����A��͂荇���������Ă������������܂����B�X�L�Ԃ�����̂ł����A����͒��߂܂��B
�@�u���[�h��h��܂����B��햖���̗��R�@�͖��h�����̂��������A�����Ȃ��L�]64�̎ʐ^������Ƃ�͂薳�h���Ȃ̂ŁA�V���o�[�d�グ�Ƃ��܂����B�����Ȃ���̃N���I�X8�Ԃ��g�����Ǝv���Ă���Ƃ���ɁA���������b�ɂȂ��Ă���̒���G�A���f���[N����Ɂu�K�C�A�̃V���o�[�͂�����v�ƕ������̂ŁA�������߂̃J���[��3�F���肵�Ď����h������Ă݂܂����B
�@�K�C�A��3�F�A�����燂123�A��121�A��009�ƃN���I�X8�Ԃł��B�����̂Ƃ���N���I�X8�ԂƇ�009�͂��Ȃ莗�Ă��܂��B��121�͂���ɔ�ׂ��Ȃ�L���L���x���オ���Ă��܂��B��123�̓V���o�[�Ƃ�����艩���F�H������ƗႦ�l�̂Ȃ��F�ł��B�ʐ^�ł͂Ȃ�������܂���Ȃ��B�E�E�E�Ƃ肠�����͇�009�����C���ɂ��S�̂ɐ����A�����n�����o�����߂ɕ����I�ɇ�121���g���Ă݂܂����B
2009�@7/5�i���j
�@�X�s���i�[�Ƀu���[�h���G�|�L�V�ڒ��܂Őڒ����A�ł܂����Ƃ���ł��悢��@��ɑ����B�ʓd���܂��B�ʐ^�̂悤�ɂ��������Ă��܂��B���]���Ă���̂��͒肩�ł͂Ȃ��̂ł����A�Ƃɂ�������Ă���܂��B��͂�y����2�g�̂œd�r1�{���ƃ��������ȉ�]�ł��B�ʐ^�ł͐�^��]���ł����E�E�E�B�e���̃V���b�^�[�X�s�[�h�̐ݒ肪������ƂɂȂ肻���ł��B
�@�@����Ɍ������ĐԂ���Ȃ����܂��B�f�J�[���ɐԂ���ȃ}�[�N���܂܂�Ă���̂ł����A�h��ł����܂��B���Ɛ����������Ԃœh��A�@��ɃA���`�O���A��h��Ƃ肠�����h��͏I���ł��B�@
�@�L���m�s�[�̃}�X�L���O�����܂����B�L���m�s�[�̏�v���ƃN���A���́A��͂���o���Đ����ł����B���Ԃ�J�^�`�͂��тȂ̂ł��傤���A��Ȃ̂͂�����ƌ�����킩��܂���B
�@���̊ۂ͂Ƃ肠�����t���̃f�J�[�����g���܂��B�u�����̃f�J�[���͂ǂȂ��Ȃ��Ⴂ�v�Ƃ����ɒЂ���ƁA��肩���ȒP�ɂ���Ƒ䎆��蔍����܂����B���������ɂ��낢�B�^�~���Ȃǂ̃f�J�[���̂悤�Ȉ���������Ƒ����ɔj���Ă��܂��܂��B��舵�����ӁB
�@�A���e�i�����p���X�g�Œ����ĂƂ肠���������B�܂��͎���@�Ƃ��ĎB�e���܂��B
�@
2009�@7/31�i���j
�@�~�J���������̂Ɉ��V�������A�r���������߂���ԂŁA��ɂ���ċߏ��̉͌��Ń��P���������ƁA�r�����ăz���]���g�̏�Łi�z���]���g�ȂǂƟ��������������Ă܂����A�J�����_�[�̗��ł��B�j�u�c�B��A����ɗ����V�[�����͌��ŎB�e���܂����B
�@���܂�r��t������ԂŎʐ^���B���̂ŁA���̊����͌��\�V�N�ł��B
�@���āA���ƂЂƂ���肾�B
2009�@8/1�i�y�j
�@����ǂ��\��ʂ�B�e���I�������̂ŋr���O���t�F�A�����O����A�������Ď���Ă������L���m�s�[�ƒ������̃}�X�L���O�e�[�v���ӂ����ѓ\�肱�݂܂��B�Ō�Ƀg�b�v�R�[�g�������邽�߂ł��B



2009�@8/2�i���j
�@�f�J�[���ʼn��t�����Ă��������̊ۂ����܂��B�Z���e�[�v�Ńw�R�w�R�Ǝ���Ă����̂ł����A���\��������t�����Ă���̂łĂ�����܂����B�Ȃɂ������܂ł���Ƃ��܂��r�Ȃ��Ƃ͂ł��܂��ʁB�������ʑсA�h�����������т��}�X�L���O���ē���A�Ō�ɓ��̊ۂ��G�A�u���V�Ő����A�h��W�͑S�ďI���B�g�b�v�R�[�g�������Ċ������܂��B
�@�������Ƃ���Ő^�J�p�C�v�ō�����嗃�́w�}�C�x�߂��݁A�L���m�s�[�̃}�X�L���O�����܂��B
�@�ʐ^�̂悤�ɂ��̂܂܂ł͐F�����r�r�b�h�߂��Ă�������̂悤�Ȃ̂ŁA���p�X�e���ʼn��������܂��B���y�̃p�b�N�ō���������p�̃x�[�X�ŗl�X�ȐF�������Ă݂��̂ł����A��͂��Ԏ��R�ȉ��ꊴ���o���̂̓u���b�N�̃p�X�e���ł����B
�@����Ȃ���ȂŊ����ł��B����ɂ��Ă���Ԃ̂�����L�b�g�ł͂���܂����B�����J�����̂͐^�~�������̂ɍ���Đ^������B��͂蓌�������L�b�g�ɉ�����d���]�v���y���̃M�~�b�N�A�Ƃǂ߂̃L���m�s�[���ڂ�Ƃ����O�d��͌����܂����B���������L�b�g�Ȃǂƌ����Ă��܂��܂������A�}�j�A�b�N�ȋ@�̂������[�X���Ă��ꂽMPM�Ђɂ͊��ӂ��Ă���܂��B
�@���Ă悤�₭�V�C����N�̂悤�ɗ��������Ă����̂ŁA�ߏ��̉͌��ŎB�e�ɓ���܂��B��1�N�Ԃ�́w�����x�E�E�E���y���݂ɁB